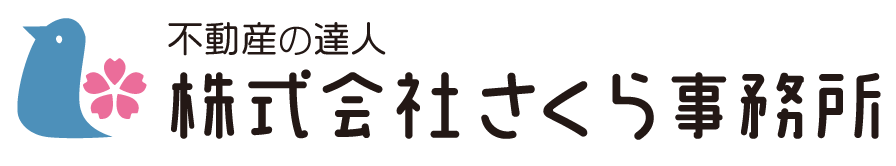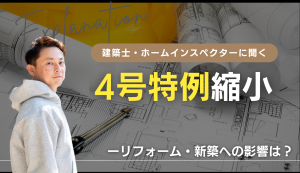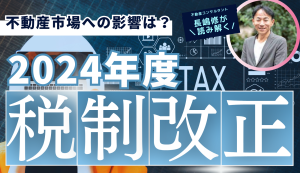マンション転売規制に空室税…自治体によるマンション政策の効果と役割とは

マンションの売買や課税は、民法や宅建業法、地方税法などによって規定されていますが、自治体が独自の規制を設けていることもあります。たとえば現在、神戸市ではタワーマンションに空室税を課すことを検討しており、千代田区では不動産協会に対し、マンションの転売を規制する要請を出しています。また神戸市では、市内のマンション管理組合に対し、修繕状況などの届け出を義務づける方針を固めているといいます。
これらの政策により、不動産価格の著しい高騰や格差の拡大、マンションの管理不全などは抑制されるのでしょうか。この記事では、自治体によるマンション政策の効果と役割を考察します。
神戸市の「タワマン空室税」
神戸市が空室のタワーマンションに対する課税を検討している背景には、投機目的によるタワーマンションの購入の増加があります。神戸市によればタワマンの高層階ほど住民登録のない部屋の割合が高く、管理組合の合意形成に支障をきたすことなどが懸念されているようですが、次のような理由から空室税を課すことによる効果は限定的と考えます。
空室のままにしておくケースは少ない
投機目的の購入が多く、実態として空室の部屋が多いということですが、空室の状態が永続的に続く部屋ばかりではないはずです。所有者が富裕層であっても、投機目的であれば貸して利益を得ようとするでしょう。売却益狙いだったとしても、何年も空室の状態にしておくのは合理的ではありません。
課税のペナルティは限定的
タワーマンションの空室に税金を課すとすれば「法定外税」という扱いになるでしょうが、固定資産税額から大きく外れた額を課税することはできないと考えられます。年間数万円から数十万円の支出は、タワーマンションの高層階を購入できるような富裕層にとって大きな負担とはならないでしょう。
とくに神戸市ではタワーマンションの建築規制をしていることもあって希少性が高く、一定の売却益を見込みやすい市場環境であることから、空室への課税が投機目的の購入の抑制にはつながりにくいものと考えられます。
「空室にしない=適正管理」には結びつきにくい
マンションが管理不全に陥るのは、空室が多いからではなく所有者の管理意識によるものです。空室税を課して借主が入ったところで、所有者の意識が変わるとは限りません。
神戸市「修繕状況等届け出義務化」
神戸市では、タワマン空室税の導入の検討に加え、市内のマンション管理組合に対し、修繕状況などの届け出を義務づける方針を固めています。同市では2021年から任意で修繕状況などの届け出を求めていますが、届け出はわずか2割程度に留まっていることもあって、これを義務化する方針です。具体的には、6戸以上の分譲マンションの管理組合を対象に、5年ごとの届け出を求めるようです。
管理意識の向上に期待できる
2020年にスタートした管理計画認定制度および管理適正評価制度の登録・更新には、一定の頻度で修繕計画を見直す必要がありますが、両制度に登録できない・登録しないマンションも少なくありません。市が修繕条件などの届け出を義務づけることで、認定制度などに未登録のマンションの管理意識を高める効果に期待できるため、個人的にはポジティブに評価しています。
届け出の「先」のフォローを
ただ、届け出自体が目的になってしまっては意味がありません。神戸市では、管理状況を届け出るメリットとして管理状態を把握・整理できることなどを挙げていますが、届け出の内容が良くなかった場合のフォロー体制が充実してくるとより良い施策となるはずです。また、こうした良い取り組みこそ神戸市だけで終わらせるのではなく、改善しながら全国に普及していくとより有益な政策になっていくでしょう。
千代田区「マンション転売規制」
千代田区は7月、投機目的のマンション取引が増えることによる過度な住宅価格の高騰などを抑制するため、不動産協会に対し、以下の要請を出しました。
- 総合設計などの都市開発諸制度を活用する事業及び市街地再開発事業(これから許認可等を受ける事業とし、以下「再開発等事業」という。)において販売するマンションについては、購入者が引き渡しを受けてから原則5年間は物件を転売できないように特約を付すこと。
- 上記1のほか、再開発等事業において販売するマンションについては、同一建物において同一名義の者による複数物件の購入を禁止すること。
(出典:千代田区「千代田区内の投機目的でのマンション取引等に関する要請について」)
また中野区も2025年9月、千代田区の政策の影響を見定めたうえで今後検討していく必要があるとの見解を示しました。
「転売規制」については、空室税のような間接的な規制と比べると、投機目的の購入を抑止する効果に期待できるでしょう。一方で、マーケットに影響するのは新築マンションだけではありません。近年は中古住宅市場が拡大していることもあって、再開発事業に伴って開発された新築マンションの転売を規制するだけでは、不動産価格高騰の抑止効果は限定的であると言わざるを得ません。
マンションを取り巻く根本的な問題の解消に必要なこと
空室税の導入にしても転売規制にしても、神戸市や千代田区など一つの自治体による政策では、不動産価格の著しい高騰や投機的のマンション購入の増加、管理不全といった問題の根本的な解決には至りません。たとえば「千代田区で転売が規制されるのなら港区で買えばいい」「神戸市で空室税が課されるなら大阪で買う」といったことにもなりかねず、逆に局所的な需要の低減やマンション価格の下落、それらによる格差拡大に結びついてしまうおそれもあります。
ある程度まとまったエリアで同一の施策を
とはいえ、マーケットは地域特性があることから、画一的な政策だけではマンションを取り巻く課題の根本的な解決はできないでしょう。したがって、国としての方向性を示したうえで、自治体独自の取り組みというよりも「23区」や「政令都市」などある程度まとまったエリアが同一の対応をしていくことが有効であると考えます。
ペナルティだけでなくインセンティブを
また、自治体による政策の多くは「規制の引き締め」や「ペナルティ」ですが、併せて「インセンティブ」を与える施策があってもいいと思います。空室を減らし、管理不全が起きないようにするには、新陳代謝を高める、つまり流通の促進が効果的です。たとえば、売買する人に今より手厚い税制等の優遇をすることなどがインセンティブになってくるのではないでしょうか。
目指すべきは「共存共栄」
昨今、外国人による日本の不動産購入が問題視される側面もありますが、デメリットばかりではないはずです。これから日本では少子高齢化が加速していく中で、日本の内需だけでは土地や建物の価値を維持・向上させていくことはできません。不動産の価値や経済面でいえば、日本の不動産市場に海外マネーが入ってくるメリットは一定あります。
とはいえ、日本の一般的な収入の世帯が不動産を購入できなくなってしまう事態は避けなければならず、ここでもやはりペナルティとインセンティブのバランス、そして国レベルの統一的な政策に加え、地域特性に応じた詳細な制度設計が重要になってくると考えます。
まとめ
政策を推進していくうえでは、管理の問題や投機目的の購入が増えている問題、格差を生んでいる問題などを分けて考えなければなりません。たとえば、投資家や外国籍の方の所有者が増えることが直接的な要因となってマンションの管理を悪化させるわけではないはずです。また、外国人による日本の不動産の購入も悪い面ばかりがフューチャーされていますが、日本の経済や不動産市場にとって良い側面もあります。エリアや国籍、収入、売買の目的等問わず、不動産市場に関わるすべての人が共存共栄できるような市場環境の構築こそが、国や自治体の役割になってくるのではないでしょうか。