住宅購入において「この家は本当に安全なのか」「省エネ性能は十分なのか」といった不安を
感じたことはありませんか。
そんな疑問を解決してくれるのが「住宅性能評価」です。
国が定めた統一基準により、第三者機関が客観的に住宅の性能を評価・証明する制度で、
金利優遇や保険料割引など実用的なメリットも数多く得られます。
本記事では、住宅性能評価制度の仕組みから具体的な取得方法、注意点まで詳しく解説します。
住宅性能評価とは?

住宅性能評価とは、国が定めた「住宅性能表示制度」に基づいて住宅の性能を第三者機関が客観的に評価する制度です。住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づいて運用されており、住宅購入者の安心・安全な住宅取得を支援することを目的としています。
評価項目には新築住宅の場合は10分野33項目で評価され、耐震性、省エネ性、維持管理の容易さ、劣化対策などが含まれ、設計図や現場検査に基づいて総合的に判定されます。購入者や施主が住宅の性能を客観的に把握でき、住宅の品質を見える化する重要な仕組みとなっています。
設計住宅性能評価とは
設計住宅性能評価書は、設計図書や仕様書をもとに、登録評価機関が耐震性・省エネ性などを審査し、着工前に性能を評価するものです。設計段階で性能が明確になるため、契約内容に性能を反映でき、トラブル防止につながります。住宅を建てる前の設計段階で性能を確認できるため、建築主は安心して工事を進めることができ、万が一設計に問題があった場合も早期に対応できるメリットがあります。
建設住宅性能評価とは
完成後の住宅を実際に現地で検査し、設計図通り施工されているかを評価する仕組みです。複数回の工程検査により施工品質を担保し、性能評価書の交付を受けることが可能です。建設段階では、基礎工事、構造躯体工事、内装工事など、各段階で専門の検査員が現場に赴き、設計図書通りに施工されているかを詳細にチェックします。これにより、設計上の性能が実際に実現されていることを確認できます。
住宅性能評価の評価項目は10個

住宅性能評価では、住宅の性能を10の分野に分けて体系的に評価します。各分野には必須項目と選択項目があり、住宅の種類や用途、建築主のニーズに応じて適切な評価が行われます。この統一された評価基準により、住宅の性能を客観的かつ数値的に比較検討することが可能となります。
構造の安定
地震や風・積雪等の自然災害に対する住宅の耐久性評価です。特に地震については耐震等級1~3で評価され、等級3が最高ランクとなります。具体的には、耐震等級1は建築基準法レベルの耐震性能、等級2はその1.25倍、等級3は1.5倍の耐震性能を持つことを示しています。
近年の大規模地震を踏まえ、多くの住宅購入者が最も重視する項目となっています。地震大国日本では特に重要な評価項目といえるでしょう。さらに、基礎や柱、梁などの構造部材の配置バランスや接合部の強度なども詳細に審査され、総合的な構造安全性が数値化されます。
火災時の安全
火災の発生防止対策、避難のしやすさ、延焼のしにくさを総合的に評価する項目です。具体的には、火災報知器の設置、避難経路の確保、開口部等の耐火性能、延焼対策など、多面的に火災から命と財産を守る性能を審査します。
特に高層住宅や密集市街地では、火災時の安全性確保が重要な課題となるため、この評価項目の重要性がますます高まっています。そこで、建材の不燃性や避難経路の確保状況が詳細に評価されるほか、階段の幅や手すりの設置状況、バルコニーから他住戸への避難の可能性なども総合的に判断されます。
劣化の軽減
住宅の柱、壁、土台、基礎等の構造躯体が長期間良好に維持されるかを評価します。ここで重要なのは、建物の構造によって求められる対策が異なることです。例えば、木造住宅では防腐・防蟻処理、鉄骨造では防錆対策、鉄筋コンクリート造ではコンクリートの品質管理など、構造に応じた劣化対策の実施状況が重要な評価ポイントとなります。
また、通気層の確保や防湿シートの施工状況なども詳細にチェックされ、建物の長期的な耐久性向上を図ります。これらの対策により、住宅の価値を長期間維持できるようになるのです。
維持管理・更新への配慮
建物の性能維持には日常的なメンテナンスが不可欠です。そのため、給排水・ガス管などの点検・補修のしやすさ、共用配管の清掃更新の容易性、間取り変更への配慮など、将来のメンテナンスに適した設計かどうかを評価します。
住宅は建てた後のメンテナンスが重要だからです。そこで、配管の点検口設置、更新時の工事のしやすさ、将来のライフスタイル変化に対応できる設計など、長期的な視点での評価が行われます。特に配管類のアクセスしやすさや間取り変更の可能性が重視され、これらが適切に配慮されていることで、将来的な維持費用の軽減や住みやすさの維持につながります。
温熱環境・エネルギー消費量
環境性能の観点から、断熱等性能や一次エネルギー消費量の両面で評価し、環境性能を数値化します。これは2025年の省エネ法義務化や2030年ZEH推進と整合したエネルギー効率性を示すものです。
断熱性能の向上は冷暖房費の削減だけでなく、住環境の快適性向上にも直結するため重要です。実際に、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)の普及とともに、この評価項目への注目が高まっており、外皮性能と設備機器の効率性が総合的に評価されます。
空気環境
健康面では、住宅内の空気の質を保ち、健康的な暮らしを実現するため、ホルムアルデヒド発散量や換気装置による換気回数など、室内化学物質対策と換気設備を評価します。
というのも、シックハウス症候群の予防や、新型コロナウイルス感染拡大を機に注目された換気性能など、室内空気質の重要性が広く認識されるようになったからです。そこで、建材からの化学物質放散量の測定や、24時間換気システムの性能が詳細にチェックされ、住む人の健康に配慮した住環境が確保されているかを確認します。
光・視環境
居住快適性の面では、開口部の面積と方位別比率により採光・眺望性能を評価します。自然光利用や視界の開放感を図面と現地により評価し、居住快適性を確認できます。
なぜなら、自然光の取り入れ方は、住宅の快適性や省エネ性に大きく影響するからです。また、眺望や開放感は住まいの質を左右する重要な要素として評価されます。そのため、各居室の窓面積や配置、隣地との関係などが総合的に判断され、明るく開放的な住環境が実現されているかをチェックします。
音環境
共同住宅では特に重要なのが、建物の重量床衝撃音や界壁の音漏れなど、上下階や隣戸の騒音を遮断する性能の評価です。防音性の数値的根拠で、住環境の静音性を明確化します。
特に共同住宅(マンション等)では重要視される項目です。というのも、近隣トラブルの原因となりやすい騒音問題を未然に防ぐためには、建材の遮音性能や施工方法の詳細な評価が必要だからです。そこで、床材の厚さや壁の構造、開口部の仕様などが審査対象となります。
高齢者等への配慮
将来への備えとして、段差2cm以下、手すり設置、玄関や浴室などのスペース確保など、バリアフリー設計において介助や移動がしやすい住宅設計かを多面的に評価します。
高齢化社会の進展に伴い、将来の身体機能の変化に対応できる住宅設計の重要性が高まっているからです。そのため、車椅子での移動や介助のしやすさなど、様々な視点から評価されます。廊下幅や扉の仕様、浴室の段差解消などが具体的な評価ポイントです。
防犯
外壁開口部の侵入防止対策や防犯設備有無により、不審者侵入を抑止できる防犯性能を評価し、安全性を担保します。具体的には、窓やドアの防犯性能、外構計画、防犯カメラの設置など、住宅への不法侵入を防ぐための総合的な対策が評価対象となります。特に1階部分の開口部については、防犯建物部品(CPマーク製品)の使用状況や、外部からの見通しなどが重要な評価項目となります。
住宅性能評価を受けた住宅に対するメリット
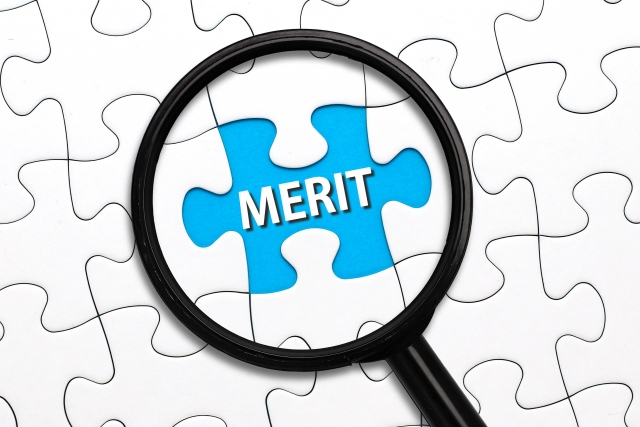
住宅性能評価を取得することで、様々な経済的・実用的なメリットを享受できます。これらのメリットは評価取得にかかる費用を上回る価値をもたらすことが多く、住宅取得の総合的なコストパフォーマンス向上につながります。以下、具体的なメリットを詳しく見ていきましょう。
民間金融機関による住宅ローン金利引き下げ
まず、住宅性能評価書を取得した住宅は、フラット35などの住宅ローン金利が優遇されるケースがあります。これは、性能が保証されるため、金融機関のリスクが軽減されるためです。長期間にわたる住宅ローンの支払いにおいて、わずかな金利の差でも総支払額に大きな影響を与えます。実際に、性能評価取得により金利優遇を受けられれば、大幅な節約効果が期待でき、金利0.1%の差でも数十万円の違いが生まれることもあります。
耐震等級に応じた地震保険料の割引
さらに、耐震等級が高い住宅は、地震保険料の割引が適用されます。等級が上がるほど割引率が大きくなり、住宅の耐震性能が経済的メリットにもつながります。例えば、耐震等級3の住宅では地震保険料が50%割引となるなど、大幅な保険料削減が可能です。地震リスクの高い日本において、この割引制度は大きなメリットとなり、年間数万円の保険料削減効果があるため、長期的には大きな節約につながります。
贈与税の非課税枠の拡大
また、住宅性能評価書のある住宅は、住宅取得時の贈与税非課税枠が拡大される特例を受けられる場合があります。これにより、相続や贈与の節税効果が見込めます。特に、親世代から住宅取得資金の援助を受ける場合、通常の非課税枠を超える部分についても非課税扱いとなることがあり、税負担の軽減につながります。つまり、質の高い住宅を取得することで、より多くの資金援助を非課税で受けることが可能となり、家計負担の軽減に大きく貢献します。
住宅瑕疵保険の加入手続きの簡素化
性能評価を受けた住宅は、瑕疵保険の加入がスムーズになり、万が一の欠陥発見時の補償が確実になります。住宅瑕疵保険は、住宅の構造上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分に欠陥があった場合の修補費用を補償する保険です。性能評価を受けることで、保険加入の審査が簡素化されます。また、保険会社からの信頼度も高まり、保険料の優遇措置を受けられる可能性もあります。
長期優良住宅の認定手続きの簡素化
性能評価の取得は長期優良住宅認定の申請に有利に働き、手続きの簡略化や認定取得の可能性が高まります。長期優良住宅の認定を受けると、住宅ローン控除の拡大や不動産取得税の軽減など、さらなる税制優遇措置を受けることができます。性能評価書があることで、認定に必要な技術的審査の一部が省略されるため、申請手続きの負担軽減と審査期間の短縮が期待できます。結果として、より確実に長期優良住宅認定を取得できます。
専門機関にトラブルの相談ができる
住宅性能評価書があると、指定住宅紛争処理機関への相談が可能となり、トラブル発生時に第三者の仲介を得やすくなります。住宅に関する紛争が発生した場合、専門知識を持つ第三者機関が調停や仲裁を行うため、公正で迅速な解決が期待できます。通常の裁判と比べて費用が安く、専門性の高い解決が可能です。建築や不動産の専門家が関与するため、技術的な問題についても適切な判断が期待できます。
売却時に優位になる
住宅の性能が証明されているため、中古住宅市場での信頼性が高まり、資産価値の維持や売却時の競争力向上に役立ちます。将来住宅を売却する際、性能が客観的に証明されていることで、購入希望者に対する訴求力が高まり、適正な価格での売却が期待できます。特に築年数が経過した住宅でも、性能評価書があることで品質への信頼性が保たれ、他の物件との差別化が図れます。結果として、より良い条件での売却が可能となります。
住宅性能評価を取得するためには?

住宅性能評価を取得するには、段階的なプロセスを踏んで計画的に進める必要があります。適切な手順を理解し、必要な準備を整えることで、スムーズかつ確実な取得が可能となります。建築スケジュールとの調整も重要な要素となるため、以下の手順を参考に進めてください。
STEP1. 住宅性能評価制度を理解する
まずは住宅性能評価制度の目的や評価の種類、評価項目を理解すべきです。設計評価と建設評価があり、それぞれの特徴や取得タイミングを把握することで、取得計画をスムーズに進められます。制度の仕組みを正しく理解することで、どの評価項目を重視するか、どのタイミングで申請するかなど、戦略的な取得計画を立てることができます。また、評価にかかる費用や期間も事前に把握しておくことで、資金計画や工程計画に反映させることが可能です。
STEP2. 2つのうちどちらの評価を受けるのかを確認する
設計住宅性能評価は設計段階、建設住宅性能評価は施工段階に取得します。どちらか一方だけでも取得可能ですが、両方取得すると住宅の性能をより確実に証明できるため、目的に応じて選択が重要です。設計評価のみの場合は着工前に性能を確認できますが、実際の施工品質は保証されません。建設評価も併せて取得することで、設計通りの性能が実現されていることを客観的に証明でき、より高い信頼性を得ることができます。
STEP3. 評価機関の選定と申込
国土交通省に登録された評価機関の中から住宅の種類や目的に応じて選びます。地域性や評価実績も参考にするとよいでしょう。評価申請は早めに行うのが望ましく、書類不備や審査遅延を防ぐため、事前の相談や必要書類の準備も欠かせません。評価機関によって得意分野や対応エリアが異なるため、複数の機関から見積もりを取得し、費用やサービス内容を比較検討することが重要です。また、設計者や施工者との連携体制も確認しておきましょう。
STEP4. 必要書類の準備
設計図面や仕様書、構造計算書など評価に必要な書類を揃えます。不備があると審査が遅れるので、専門家のアドバイスを受けながら丁寧に準備しましょう。評価項目ごとに提出物が異なります。特に構造計算書や省エネ計算書など、専門的な書類が必要となるため、設計者との綿密な打ち合わせが不可欠です。また、書類の記載内容に矛盾がないよう、事前のチェックを十分に行うことで、審査をスムーズに進めることができます。
STEP5. 評価機関による審査・検査
設計評価は書面審査、建設評価は施工中の現場検査も含まれます。評価基準を満たしているか厳しくチェックされ、場合によっては追加資料提出や補正指示があるため、迅速な対応が必要です。現場検査では、基礎工事、構造躯体工事、断熱工事など、各工程で検査が実施されます。検査に合格しない場合は補修工事が必要となることもあるため、施工者との連携を密にし、品質管理を徹底することが重要です。
STEP6. 住宅性能評価書の交付
審査をクリアすると住宅性能評価書が交付されます。交付後は住宅購入者や金融機関へ提示し、住宅ローンや保険の優遇措置申請に活用できます。交付までのスケジュール管理も重要です。評価書は住宅の品質を証明する重要な書類となるため、大切に保管する必要があります。また、将来の売却時にも必要となるため、紛失しないよう注意が必要です。評価書の内容について不明な点があれば、評価機関に確認することをお勧めします。
住宅性能評価書の取得にかかる期間と費用
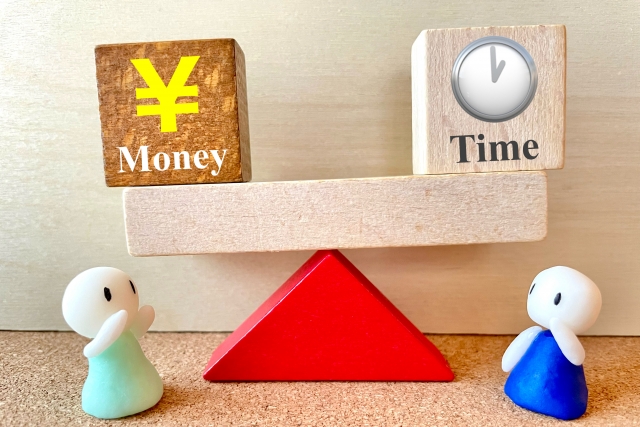
住宅性能評価書の取得を検討する際、期間と費用の把握は重要な要素です。これらは住宅の規模や評価項目、評価機関によって大きく変動するため、計画段階での十分な検討が必要です。適切な予算とスケジュールを組むために、以下の目安を理解しておきましょう。
取得までに数カ月かかる場合がある
住宅性能評価書の取得は、設計段階の申請から建設完了後の現場検査まで複数のプロセスを経るため、一般的に数カ月かかることがあります。特に設計評価と建設評価の両方を取得する場合、設計図書の作成や修正、検査の日程調整なども加わり、スケジュールが延びることがあるため、余裕を持った計画が不可欠です。また、審査や検査の結果によっては追加資料の提出や再検査が必要となり、さらに時間がかかる場合もあります。
費用は住宅の規模や評価範囲によって異なる
取得にかかる費用は、住宅の延床面積や構造の複雑さ、評価を受ける項目数によって大きく変わります。戸建て住宅の場合、設計評価・建設評価の双方を合わせて数十万円が相場ですが、より大規模な住宅や特殊な構造の場合はそれ以上になることもあります。評価機関によって料金設定やサービス内容が異なるため、複数の機関から見積もりを取り、費用対効果を比較検討することが重要です。
住宅性能評価書取得時の注意点

住宅性能評価書を取得する際には、制度の特性を理解した上で進めることが重要です。期待する効果を確実に得るためにも、以下の注意点をしっかりと把握しておきましょう。これらのポイントを理解することで、より効果的に制度を活用できます。
設計評価と建設評価はセット取得が基本
設計評価だけでは性能の実現が確認できないため、施工品質を保証する建設評価も取得するのが推奨されます。設計図面上では優れた性能を示していても、実際の施工において設計通りに建設されなければ、期待した性能は得られません。両方の評価を取得することで、設計から施工まで一貫した品質管理が可能となり、住宅の性能を総合的に保証することができます。また、金融機関や保険会社からの信頼性も高まり、各種優遇措置をより確実に受けることができます。
評価等級=性能そのものではない
評価書の等級はあくまで審査基準を満たしたかの指標であり、住宅の全性能や快適性を保証するものではありません。評価項目以外の要素(デザイン性、使い勝手、周辺環境など)も住宅の価値を左右する重要な要素です。評価結果を参考にしながらも、総合的な視点で住宅を評価することが大切です。また、評価基準は最低限の性能を保証するものであり、より高い性能を求める場合は評価基準を上回る仕様を検討することも重要です。
リフォームや既存住宅には別制度が適応される
設計住宅性能評価は新築住宅向けの評価制度であるため、中古住宅やリフォーム住宅は「既存住宅性能評価」など別の評価制度が適用されます。申請内容や審査方法も異なります。既存住宅では現況調査が中心となり、新築時とは異なる評価基準が適用されます。リフォームを検討している場合は、既存住宅性能評価制度について理解し、適切な評価機関に相談することが重要です。制度の違いを理解せずに申請すると、期待した結果が得られない可能性があります。
まとめ

住宅性能評価制度は、住宅の品質を客観的に評価し、安心・安全な住宅取得を支援する重要な制度です。10の評価分野により住宅の性能を総合的に判定し、金利優遇や保険料割引などの経済的メリットも享受できます。取得には数カ月の期間と相応の費用がかかりますが、長期的な視点では十分な価値があります。設計評価と建設評価のセット取得が基本であり、評価等級は性能の一つの指標として捉えることが大切です。
ただし、住宅性能評価制度は複雑で、どの評価項目を重視すべきか、評価書をどう読み解くかなど、専門的な判断が必要な場面も多くあります。
住宅取得は人生最大級の買い物だからこそ、制度を上手に活用して後悔のない選択をしたいものです。さくら事務所では、建築士などの資格を持った専門家が「住まいの専門家相談」にて、住宅性能評価制度の活用方法について中立的な立場でアドバイスしています。
また、合わせて第三者による客観的な品質チェックも行うことで、安心できる住宅取得をトータルサポートいたします。
⇒さくら事務所のホームインスペクション






