住宅のリフォーム・購入を検討している方にとって、気密性や断熱性の向上は大きな選択肢となるでしょう。しかし、高気密高断熱住宅にするとどんな効果があり、どんな問題が起こりうるのか、判断材料がなければリフォームの決断は難しいものです。
この記事では、高気密高断熱住宅の特徴やメリット・デメリット、断熱工法の種類や工事費用、そして住む際の注意点まで詳しく解説します。これから住宅性能の向上を考えている方にとって、リフォーム決断の一助となる情報をご提供します。
高気密高断熱住宅の特徴

高気密高断熱住宅とは、文字通り気密性や断熱性が高い住宅のことであり、これらの性能をともに高めることで、エネルギーの消費効率が良くなった上で、夏冬ともに快適な室温で過ごすことができます。以下では、高気密住宅と高断熱住宅に関して詳しく解説していきます。
高気密住宅は外気が室内に入りづらい
高気密住宅とは、壁の内側や床下などに、断熱材や防湿シート、気密テープなどを隙間なく施工して外気の出入りを最小限に抑えた住宅のことを指します。住宅内の隙間が埋められているため、外気が室内に入りづらく、室内の空気も外へ逃げづらいという特徴があります。
これにより、冷暖房の効率が格段に向上し、一度設定した室温を長時間維持することができます。また、外部からの花粉やホコリ、騒音などの侵入も防ぎやすくなるため、アレルギー対策や静かな住環境を求める方にも適しています。
高断熱住宅は外気温の影響を受けづらい
高断熱住宅は、屋根や天井裏、壁の内側、床下などに断熱材を詰め、断熱性能を向上させた住宅のことを指します。外の気温の影響を受けづらいため、夏は涼しく、冬は暖かい室温を保つことが可能です。
断熱性能が高いと、室内の温度変化が緩やかになり、特に冬場の「寒い家」という不快感を大幅に軽減できます。また、家全体の温度差が少なくなるため、ヒートショックのリスクも減少します。
高気密高断熱住宅のメリット

高気密高断熱住宅に住むメリットは以下の6つです。
光熱費が削減される
高気密高断熱住宅では、外気の影響を受けづらく、室内の空気も逃げづらいため、エアコンの温度を一定に保ち、エネルギー効率を向上させられます。また、夏は高く、冬は低いエアコンの設定温度でも、快適に過ごせるため光熱費の削減につながります。
一般的な住宅と比較すると、年間の冷暖房費を大幅に削減できるケースも少なくありません。長期的に見れば、初期投資の回収も十分可能であり、地球環境への負荷軽減にも貢献できる点は大きなメリットといえるでしょう。
住宅性能を維持しやすい
外気からの影響を受けづらく、室内に低温部ができにくいことから結露の発生などを防げます。結露が発生すると、建材の劣化やカビの原因となり、最悪の場合、健康被害や住宅性能の劣化を引き起こします。詳細は後ほど解説しますが、床下や天井裏、壁で発生する内部結露のリスクリスクには十分注意すべきです。
適切な断熱・気密工事により住宅の寿命が延び、長期的な維持管理コストの削減にもつながります。特に木造住宅では、湿気によるダメージを防ぐことで、構造体の劣化を抑制する効果も期待できます。
洗濯物が乾きやすい
高気密高断熱化した住宅は室内の温度及び湿度が安定する傾向があり、窓からの自然換気ではなく、計画的な機械換気システムを併用しています。そのため、室内に適度な気流が発生することで、室内干しに適した環境を生み出しています。
ヒートショックのリスクが低減される
ヒートショックとは、急激に温度が変化することで、血圧の急上昇急降下を引き起こし、最悪の場合心肺停止などを引き起こす現象です。気密性や断熱性が高い場合、室内の温度が一定に保たれるため、温度差が生まれにくく、ヒートショックが起きにくくなります。
特に高齢者にとって、冬場の暖かいリビングから寒い浴室への移動は危険を伴いますが、高気密高断熱住宅では家全体の温度差が小さくなるため、安全性が高まります。これは将来を見据えた健康投資と言えるでしょう。
防音効果がある
断熱材により、室内の音が外に漏れづらくなります。同じく、外からの音もシャットダウンされやすいです。断熱材の種類によって吸音性能は異なりますが、一般的に高断熱住宅では遮音性能も向上します。
都市部や交通量の多い道路近くでは、外部騒音の軽減は生活の質を大きく向上させる要素となります。また、家族それぞれの生活音も緩和されるため、プライバシーの確保にも役立ちます。
中古住宅市場でも評価されやすい
気密性や断熱性は、省エネ法による基準を基に等級が定められています。新築住宅は最新の省エネ基準に基づき着工されるため、住宅性能が低い場合、一昔前レベルの住宅だとして、中古住宅市場でも評価されづらくなります。気密性や断熱性が高ければ、むしろ性能が良い住宅として価値が下がりづらくなります。
住宅の資産価値を保つという観点からも、高気密高断熱リフォームは有効な選択肢と言えるでしょう。特に2025年4月以降の省エネ基準適合の義務化に向けて、断熱性能の高さは住宅の付加価値として重要性が増しています。
高気密高断熱住宅のデメリット

高気密高断熱住宅に住むデメリットは以下の3つです。
建築・改築費用が高額になる
工事費用だけでなく、断熱材など専門の資材分の費用もかかるため、高額になりやすいです。しかし、光熱費の削減などにもつながるため、長期的視点で考えることが大事です。事前に業者に見積もりを依頼し、費用を把握しておくべきでしょう。
一般的なリフォームと比較すると、高気密高断熱リフォームは100万円〜数百万円の追加コストがかかる場合があります。ただし、補助金制度を活用することで、一部コストを軽減できる可能性もあります。
内部結露につながる可能性がある
断熱工事をしても、住宅に少しの隙間ができる可能性があります。そうすると、室内の暖かい空気がその隙間に入り、壁内や天井裏などで結露を起こす可能性があります。そうなるとカビやシロアリの発生原因となるため、工事を依頼する際は丁寧に施工してくれる業者を選ぶべきです。
内部結露は夏と冬でも発生のメカニズムが異なり、断熱材によってできる温度差の部分で結露が起こらないようにするには、防湿と湿気の排出についての適切な計画と施工が必要となるため、換気システムを導入するなどの対策も必要です。施工品質が低いと、想定外の箇所で湿気が溜まり、長期的な住宅ダメージにつながる恐れがあります。
メンテナンスコストがかかる
気密性や断熱性が高いゆえに、室内の空気がこもりやすいです。そのため、内部結露だけでなく、ハウスダストが空気に多く含まれダニの発生原因ともなりやすいです。換気システムなどの導入が必要となるなど、メンテナンスが必要となります。
高気密高断熱の住宅はその性能を生かすためには、窓の開け閉めでの換気ではなく、熱交換型等の換気扇の使用が望ましいため、機械換気の重要度は高くなります。フィルター等のメンテナンスが適切に行われないと、換気能力も低下して、湿気の排出や室内の塵埃排出にも影響がでるため、手間やコストがかかる傾向にあります。
断熱工法には「内断熱」と「外断熱」がある
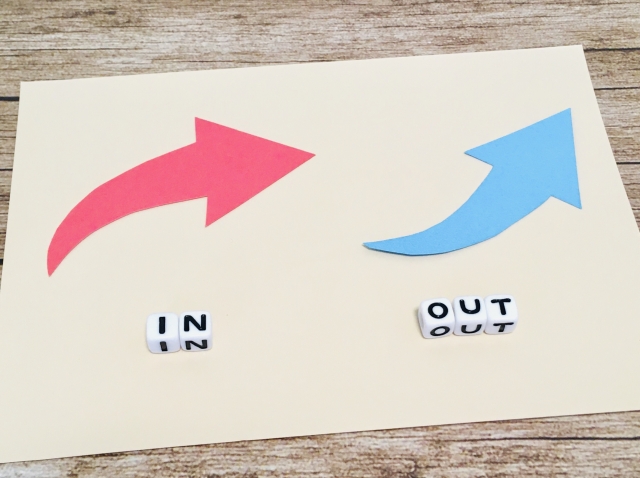
断熱工法には「内断熱」と「外断熱」の2つがあります。詳細は以下で解説していきます。
内断熱はコストを抑えやすい
内断熱とは充填断熱と呼ばれ、建物内部に断熱層をつくる工法です。外壁と室内の壁との間のほか、天井や床下などに断熱材を詰めて住宅の断熱性を高めます。コストが抑えやすく、内装工事と共に行える点はメリットです。しかし、工事の仕方により壁や外壁の間に隙間ができてしまうこともあり、気密性は確保しづらくなりやすいです。
断熱材が構造体の内側にあるものが内断熱になるので、木造では壁内の充填断熱が一般的ですが、RC造等は内側に吹き付け等をしている場合が多いので、内断熱=充填断熱とはならない点に注意が必要です。
既存住宅のリフォームでは、内装を解体する必要があるため、全面的なリノベーションと合わせて行うと効率的です。部分的な改修も可能なため、予算や生活スタイルに合わせて段階的に進めることができる点も魅力です。
外断熱は気密性を確保しやすい
外断熱とは、住宅を覆うように建物の構造体の外側に断熱層をつくる工法です。内断熱よりも気密性が高く、構造物が傷みにくいです。また、壁内に断熱材を詰める必要がないため、内部結露が起こりにくくなります。
一方、内断熱に比べてコストが高いです。また、建物の外側を断熱材で覆う必要があるため、外壁が厚くなりやすいです。気密性が高い分、換気の重要度が高くなります。
外断熱は、構造体自体が外気温の影響を受けにくくなるため、建物の耐久性向上にも貢献します。特にRC造の建物では、コンクリートの温度変化による収縮・膨張が抑えられ、ひび割れの発生を防止する効果も期待できます。
断熱材は大きく3種類に分けられる

断熱材は大きく分けて無機繊維系、木質繊維系、発泡プラスチック系の3種類があります。それぞれの特徴を見ていきましょう。
無機繊維系
無機繊維系断熱材には、主にグラスウールとロックウールがあります。
グラスウールは、リサイクルガラスを原料とした繊維状の断熱材で、軽量かつ安価であることが特徴です。防火性能も高く、壁や天井の断熱に広く使用されています。一方、湿気に弱いため、防湿対策が必要です。
ロックウールは、玄武岩などの天然鉱物を原料とした繊維状の断熱材で、耐火性・耐熱性に優れています。音の吸収性能も高く、防音効果も期待できます。グラスウール同様、湿気対策が必要となります。
木質繊維系
木質繊維系断熱材には、セルロースファイバーとインシュレーションボードがあります。
セルロースファイバーは、古紙などを原料とした繊維状の断熱材で、環境負荷が低いエコ素材です。調湿性能に優れ、壁内の湿度を適切に調整する効果があります。また、隙間なく充填できるため、気密性確保にも貢献します。
インシュレーションボードは、木材チップなどを圧縮して板状にした断熱材で、断熱性と構造的な強度を兼ね備えています。自然素材のため、シックハウス症候群の原因となる化学物質の発生が少ないことが特徴です。
発泡プラスチック系
発泡プラスチック系断熱材には、硬質ウレタンフォーム、フェノールフォーム、ポリエチレンフォームなどがあります。
硬質ウレタンフォームは、高い断熱性能を持ち、吹き付けタイプは隙間なく施工可能です。防水性にも優れていますが、価格は比較的高めです。
フェノールフォームは、断熱性能と難燃性に優れ、薄い板でも高い断熱効果が得られます。狭いスペースでの断熱に適していますが、コストは高めです。
ポリエチレンフォームは、軽量で加工しやすく、水に強いという特徴があります。反発力があるため、隙間なく施工しやすい点もメリットです。主に床下や配管まわりの断熱に使用されます。
気密・断熱性能を上げる工事費用は150万〜300万円

高気密高断熱リフォームの費用は、住宅の規模や既存の性能、選択する工法や材料によって大きく異なりますが、一般的な戸建て住宅(30坪程度)の場合、150万円〜300万円程度が相場となっています。
内訳としては、断熱材費用が50万円〜100万円、気密工事費用が30万円〜50万円、窓の断熱改修費用が50万円〜100万円、換気システム導入費用が20万円〜50万円程度となることが多いです。また、外壁全体の断熱改修を行う場合は、さらに100万円程度上乗せされることもあります。
ただし、部分的な改修や段階的な工事計画を立てることで、初期費用を抑えることも可能です。また、国や自治体の省エネリフォーム補助金を活用することで、負担を軽減できる場合もありますので、事前に確認しておくとよいでしょう。
断熱工事の依頼先を選ぶ基準

断熱工事を依頼する業者選びは、リフォームの成功を左右する重要なポイントです。以下の基準を参考に、信頼できる業者を選びましょう。
専門知識や実績があるか
高気密高断熱リフォームは専門的な知識と技術を要する工事です。過去の施工事例や実績を確認し、どのような断熱性能を実現できたかを具体的に聞くことが重要です。可能であれば、過去の施工物件を見学させてもらうことも検討しましょう。
気密測定を行なってくれるか
気密性の確保は高断熱住宅の性能を左右する重要な要素です。工事後に気密測定(C値測定)を行い、数値で性能を確認してくれる業者を選ぶことで、施工品質を客観的に評価できます。測定結果を保証の一部として提示してくれる業者は信頼性が高いと言えるでしょう。
補助金の提案などをしてくれるか
省エネリフォームには様々な補助金制度があります。これらの制度に詳しく、申請のサポートまで行ってくれる業者を選ぶことで、工事費用の負担を軽減できる可能性があります。最新の補助金情報を把握しているかどうかも確認しておきましょう。
明朗会計か
見積もりの内容が詳細で、使用する材料や工法、各工程の費用が明確に記載されていることも重要です。追加費用が発生する可能性がある場合は、その条件や範囲についても事前に説明してくれる業者を選びましょう。また、アフターフォローの内容や保証期間についても確認することをおすすめします。
複数の業者から見積もりを取り、比較検討することで、適正な価格と品質のバランスを見極めることができます。最も安い業者を選ぶよりも、コストパフォーマンスの良い業者を選ぶことが長期的には満足度の高いリフォームにつながります。
高気密高断熱住宅に住む注意点2つ

高気密高断熱住宅に住む注意点は以下の2つです。
換気システムを導入する必要がある
シックハウス対策のための建築基準法により、新築住宅には24時間換気システムの設置が義務付けられています。特に高気密住宅では、気密性が高い分、ハウスダストや資材の化学物質が室内にこもりやすく、シックハウス症候群にもつながる可能性があります。そのため換気をこまめにすることが重要です。
高気密高断熱住宅では、単純な換気だけでなく、熱交換型の換気システムを導入することが推奨されます。これにより、室内の温度を維持しながら新鮮な空気を取り入れることができ、エネルギーロスを最小限に抑えられます。ただし、こうしたシステムには定期的なフィルター清掃などのメンテナンスが必要となります。
石油ストーブは一酸化炭素中毒のリスクがある
先述したように、空気の流れが制限されているため、石油ストーブの使用もリスクが上がります。一酸化炭素が外に逃げず室内に留まりやすくなるため、一酸化炭素中毒の危険性があります。
高気密住宅では、燃焼を伴う暖房機器(石油ストーブやガスストーブなど)の使用は避け、エアコンや床暖房など電気を使った暖房設備を選ぶことをおすすめします。やむを得ず使用する場合は、十分な換気を行い、一酸化炭素警報器を設置するなどの安全対策を徹底することが必要です。
断熱工事をする際は住宅診断でリスクを軽減しよう!

高気密高断熱住宅は光熱費削減や室内環境の快適性向上など多くのメリットがある一方で、初期投資の高さや適切な換気の必要性といった注意点も存在します。
断熱工法や断熱材の選択、信頼できる業者選びがリフォームの成功を左右します。長期的な視点で見れば、省エネ効果や健康面のメリット、住宅の資産価値維持など多くのプラス面があり、2025年の省エネ基準適合義務化に向けても有効な選択肢です。
快適で健康的な住環境を実現するためにも、専門家のアドバイスを参考に計画的なリフォームを検討しましょう。
さくら事務所では、住まいと暮らしの専門家としてホームインスペクションだけでなく様々なご相談に第三者としてご対応しております。
新築住宅のご計画や中古住宅のリノベーション計画などにおいて、建物の断熱性能に関するご相談やセカンドオピニオンもお引き受けしておりますので、ご希望があれば「住まいの専門家相談」のサービスをお気軽にご利用ください。
























