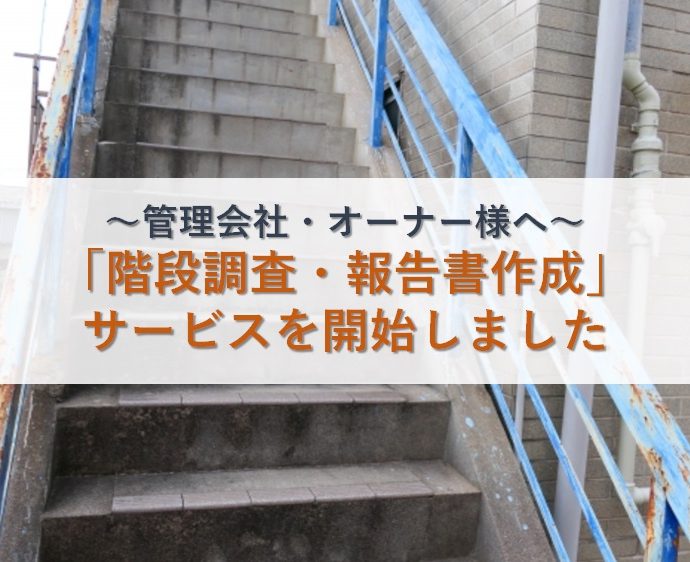地鎮祭とは、土地を守る神様に工事の承諾を得て、工事中の安全や無事完成を祈願する儀式です。地鎮祭は家を建てる際にも行われますが、実際にはどのような儀式なのかわからない人も珍しくありません。
そこで本記事では、地鎮祭の概要を解説します。当日の流れや失敗しないためのポイントも解説しているので、あわせて参考にしてください。
地鎮祭とは
戸建てを建設する際によく耳にする「地鎮祭」。しかし、どのような意味が込められている儀式なのか詳しく知らない人も多いでしょう。まずは、地鎮祭の意味や歴史について詳しく見ていきましょう。
工事着工前に行われるご祈願
地鎮祭とは、建築・土木工事の前に行われる儀式のことです。土地を守る神様に建設の承諾を得て、工事中の安全や建物の無事完成を祈ります。
地鎮祭は工事が行われる前に土地を守る神様を招いて、お供え物と祈りを捧げます。神職に土地のお祓いをしていただき、施主や施工者が鍬入れや鋤入れを行って工事の無事を祈願するのが一般的です。
なお、地鎮祭は「じちんさい」と読みますが、正式には「とこしずめのまつり」といいます。
地鎮祭の歴史は古い
地鎮祭の歴史は古く、日本最古の歴史書である「日本書記」に実施した旨が記されています。日本には昔から、自然界には神様が宿っているとの考え方があり、土地に宿る神様も信仰してきました。
その精神を現代でも引き継ぎ、建物を建設する際に地鎮祭を実施するようになったのです。
地鎮祭の流れ
地鎮祭は必ずしも行うものではなく、施主の判断によります。地鎮祭を行う場合は、施工会社が主催するのが一般的で、祭場の設営もしてくれます。
地鎮祭の流れは、以下のとおりです。具体的な作法などは事前に確認しておくとよいでしょう。
- 手水
- 修祓
- 降神の儀
- 献饌の儀
- 祝詞奏上
- 散供の儀
- 地鎮の儀
- 玉串拝礼
- 撤饌の儀
- 昇神の儀
- 直会
地鎮祭のおもな参列者は、施主、設計・施工の代表者ですが、親族や来賓を招くこともできます。地鎮祭では施主自身が出番となる場面があります。当日慌てないためにも、どのような流れで儀式が行われていくのかをチェックしてみましょう。
手水(てみず・ちょうず)
まず、手水を行いましょう。手水とは、手洗いと口をゆすいで心身を清める儀式のことです。
修祓(しゅばつ)
開式の後、祭の開催に先立ち、祭壇、お供え物、神具、参列者を祓い清めます。祓う順番は祭場、神饌、玉串、斎主、祭員、施主、工事関係者、その他の参列者となることが多いです。
降神の儀(こうしんのぎ)
次に、降神の儀を行います。降神の儀とは、祭壇に建てた神籬(ひもろぎ:神様を招く場所)に、その土地を守る神様を迎える儀式のことです。神職が「オ~」と声を発して場を畏まらせ(警蹕)、神様をお招きします。
献饌の儀(けんせんのぎ)
神様が降臨したら、献饌の儀に移ります。献饌の儀とは、神様に神饌(食事)を献上する儀式のことです。神饌は米、酒、塩、水が基本で、酒や水を入れた器(瓶子、水玉)の蓋を開けるだけの簡略した所作が一般的です。。
祝詞奏上(のりとそうじょう)
神様をお供え物でもてなしたら、その土地の使用の許しを得て、工事の安全と土地・建物の安泰を祈願します。
四方祓の儀(しほうはらいのぎ)
次に、神職がお供え物(酒、米、塩)や切麻(紙や麻の破片)を、敷地の四隅と中央に撒いて清めます。祭壇前の四方を切麻で祓う場合もあります。
地鎮の儀(じちんのぎ)
土地の四隅を祓ったら、地鎮の儀を行います。地鎮の儀は施主と施工者が神様に着工を告げる儀式です。儀式には、清めた鎌(かま)、鍬(すき)、鋤(くわ)を使い、設計者と施工会社の代表、施主の3人で行うのが一般的です。
まず、円錐形の盛砂に草を立てます。設計代表者が忌鎌(いみかま)で草刈りの所作をします。そして施主が忌鍬(いみくわ)で土を掘る所作(鍬入れ)をして盛砂に穴をつくり、その穴に神職が鎮物を埋納します。最後に、施工会社の代表が忌鋤(いみすき)で土をすくう所作(鋤入れ)をして、鎮物の上に砂をかけます。いずれの所作も、「エイ、エイ、エイ」というかけ声とともに3回くり返します。
玉串拝礼(たまぐしはいれい)
次に、神様に玉串という榊の枝を捧げます。工事が無事に完了するように、関係者がひとりづつその心を神様に捧げることです。斎主、祭員、施主、工事関係者、参列員の順に行うことが多いです。
撤饌の儀(てっせんのぎ)
撤饌の儀とは献饌の儀でお供えした神饌を下げる儀式です。お酒や水を入れた器に蓋をしてお下げする儀式のことです。最後に供えたものから順にお下げしていきます。
昇神の儀(しょうしんのぎ)
お供えをお下げしたら、昇神の儀を行います。斎主が昇神詞を唱えることで、神籬にお迎えした神様を送り出します。
直会(なおらい)
そして最後に、お供えした神饌を神職と参列者でいただく直会で儀式を終えます。略式ではその場で神前にお供えしたお酒を参列者一同でいただきます。場合によっては、場所を変えて宴会や食事の席を設けます。
地鎮祭後は近隣への挨拶を行うのが一般的
地鎮祭を実施した後は、近隣への挨拶回りを行うのが一般的です。建設中は騒音やほこり、工事車両の出入りなどで近隣住民に迷惑をかけてしまうことも珍しくありません。そのため、本格的な工事が始まる前に、一言近隣住民へ挨拶をしておくのがマナーです。事前に挨拶回りをしておくことで、入居後の関係構築にもつながるでしょう。
なお、基本的には工事責任者が同伴のうえで挨拶回りを行うほうがいいでしょう。近隣住民への挨拶は自分の家を中心として両隣と裏3軒、向かい3軒を目安に行うのがベターです。トラブルを避けるために、念のため工事の影響が及ぶ範囲を確認して決めるといいでしょう。施工会社が主導となって挨拶回りをする場合も、同伴しておくことをおすすめします。
地鎮祭当日に用意するもの
地鎮祭当日は必要な持ち物がいくつかあります。以下を参考に必要なものを準備しましょう。
- お供え物
- 初穂料(玉串料)
- 神職へのお車代
- 工事関係者など参列者へのお礼
- 近隣挨拶用のお品物
ただし、上記の持ち物については、施工会社によっては不要としている物や、施工会社が準備してくれる物もあります。事前に担当者に相談してみてください。
お供え物
地鎮祭のお供え物は、米、酒、塩、魚、海草、野菜、果物が一般的ですが、神社や地域により、種類や量・数が異なり、儀式に使う杯や榊、半紙などの準備が必要な場合もあります。施主が準備する場合は関係者に確認しておきましょう。
ここでは具体的な一例をご紹介しておきます。
- 米(一合):洗米してから一晩乾燥させておく
- お酒(一升):日本酒を用意しておく、地鎮祭用ののし紙を付けておく
- 塩(一合):敷地のお清めに使用する
- 水(一合)
- 野菜(3~5種類):地面の上にできる野菜と下にできる野菜をそれぞれ1~5個用意する
- 海の幸(3種類)
- 果実(3種類)
- 盃:参列者の人数分用意する(紙コップでも代用可能)
- 榊(5本):大きめを用意する
- 半紙(20枚)
お供え物は基本的に施主が用意するものの、神社で準備してくれる場合もあります。その際は「御供物料」を渡しておくといいでしょう。
初穂料(玉串料)
初穂料とは、神職への謝礼金のことです。地鎮祭を執り行っていただくお礼として準備しておきましょう。初穂料の相場は2~5万円程度ではありますが、依頼をする神社によって金額が異なるため、事前に確認しておいてください。
神職へのお車代
神職が車で来られる場合は、初穂料とは別に「お車代」を準備しておきましょう。基本的には、1万円前後を包みます。
工事関係者など参列者へのお礼
工事関係者などに対するお礼は必須ではありません。なぜなら、施主と同じく工事の無事を祈願する立場だからです。そのため、近年では現金ではなく菓子折りを渡すケースも増えてきました。お礼を用意した際は、事前に棟梁や営業担当者に声をかけておくと安心でしょう。
近隣挨拶用のお品物
地鎮祭が終わった後に近隣への挨拶回りをする際は手土産を用意しておきましょう。500~1,000円ほどを目安にタオルやお菓子などを用意するのが一般的です。外のしで水引の上に「粗品」もしくは「御挨拶」と記載しておき、その下に施主の名前を書いておきます。
ただし、施工会社がタオルなどを準備してくれる場合もあるため、一度問い合わせてみるといいでしょう。
地鎮祭の注意点・マナー
地鎮祭の注意点やマナーは、主に以下の2つです。
- 服装はカジュアルすぎないように注意する
- 初穂料はのし袋に入れる
地鎮祭は1時間ほどで終わる儀式ではあるものの、神様に工事の安全や建物の無事完成を願う大事な儀式です。そのため、失礼のないようにマナーを守って参列するようにしましょう。
服装はカジュアル過ぎないように注意する
地鎮祭に参列する場合は、服装に注意しましょう。地鎮祭において施主の服装に決まりがあるわけではありませんが、これからお世話になる土地の神様に祈願する神事であるためフォーマルな装いが多い傾向にあります。
服装に迷うようであれば、スーツタイプのジャケットやネクタイなどを用意しておくと安心でしょう。礼服まで用意する必要はないものの、身だしなみは整えておくべきです。
なお、地鎮祭の後は近隣住民への挨拶回りを行うケースも多いため、失礼のないようにきれいめな服装を用意しておくとよいでしょう。
初穂料はのし袋に入れる
初穂料は、紅白の蝶結びが付いたのし袋に入れてお渡しするのがマナーです。地鎮祭は「くり返してもよい祭礼」に該当するため、蝶々結びの水引が付いたのし袋を利用します。そして、水引の上段に「御初穂料」、下段に施主の名前(代表者または連名)を記載しておきましょう。
地鎮祭は必須ではない
地鎮祭は必須ではなく、行うかどうかを施主の判断で決められます。実際に、都市部のエリアで戸建て住宅を建設する際は、地鎮祭を実施しないケースもあります。
しかし、地域の風習が色濃く残るエリアや祭事を重視する住民が多く住んでいるところでは、積極的に地鎮祭を執り行っているのが現状です。とくに、地域密着型の工務店ほど地鎮祭を実施しているでしょう。そのため、実施の判断に迷った際は施主のみで判断するのではなく、施工会社に相談するのがおすすめです。
地鎮祭後はいよいよ工事着工…でもその前に!
地鎮祭を無事終えたら、いよいよ着工です。「工事が始まれば、完成するのを待つだけ」と感じる人も多いでしょう。しかし、新築工事は不具合発生率が約8割ともいわれており、工事中にトラブルが発生していないか検査しておくことがおすすめです。
さくら事務所では、建物に精通したホームインスペクターが不具合の状況をチェックするサービスを提供しております。工事中にチェックしておくことで、完成後には発見できないような重大な欠陥をも未然に防げます。安心して暮らせる住まいを手に入れるためにも、ぜひさくら事務所の新築チェックサービスをご利用ください。
https://www.sakurajimusyo.com/expert/koji-check.php?ab=d-test