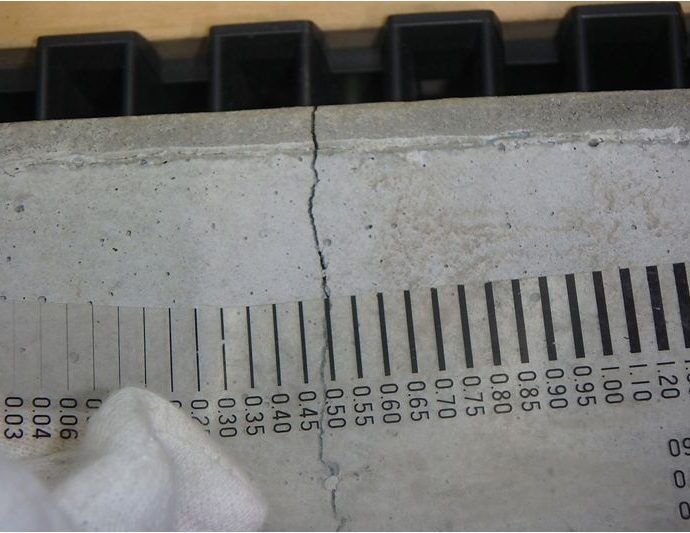住宅購入は人生で最も大きな買い物の一つです。「いくらまでなら安全に借りられるのか」「将来の生活に支障をきたさない予算はどう決めればよいのか」と悩んでいませんか。
多くの人が住宅ローンの借入可能額と返済可能額を混同し、無理な予算設定で後悔するケースが後を絶ちません。金融機関が提示する借入可能額は、必ずしもあなたの生活に適した金額ではないのです。
本記事では、家計の現状分析から将来のライフプランまでを考慮した現実的な予算設定方法を5つのステップで詳しく解説します。年収別の予算目安や住宅ローンを組む際の注意点も併せてご紹介するため、安心して住宅購入に臨めるでしょう。
【5STEP】住宅を購入する際の予算の決め方

住宅購入の予算決定は、感覚的な判断ではなく、データに基づいた計画的なアプローチが重要です。以下の5つのステップを順番に実行することで、無理のない現実的な予算を設定できます。
STEP1:家計の現状を整理する
予算設定の第一歩は、現在の収入と支出を詳細に洗い出し、住宅ローンの返済に充てられる金額を明確化することです。家計簿アプリを活用して最低3ヶ月分のデータを収集し、正確な家計状況を把握することが最初の重要なステップとなります。
収入面では、基本給だけでなく賞与や各種手当も含めた年収を算出してください。支出面では、食費や光熱費などの基本的な生活費に加え、保険料、通信費、交際費、趣味にかかる費用まで漏れなく記録します。
特に注意したいのが、年に数回しか発生しない支出です。自動車税や固定資産税、冠婚葬祭費などは月割りで計算し、毎月の支出として組み込みましょう。家計の現状を正確に把握できれば、住宅ローン返済に回せる現実的な金額が見えてきます。
STEP2:年収・頭金から借入可能額を把握する
金融機関から実際に借り入れ可能な上限額を確認します。ただし「借りられる金額」と「無理なく返済できる金額」は異なることを理解し、複数の金融機関で事前審査を受けて正確な借入可能額を把握したいところです。
融資額は前年度の源泉徴収票がベースになることが多いため、融資審査前に準備しておきましょう。個人事業主や経営者の場合は確定申告書が必要になります。
一般的に、住宅ローンの借入可能額は年収の7〜8倍程度とされていますが、金融機関によって審査基準は異なります。また、現在の借入状況や勤続年数、雇用形態なども審査に影響するため、事前審査を通じて正確な借入可能額を把握することが大切です。
頭金の額によっても借入条件が変わる場合があります。頭金が多いほど借入額を減らせるだけでなく、金利優遇を受けられる可能性もあるでしょう。
STEP3:購入にかかる総費用を知る
物件価格以外の諸費用(仲介手数料、登記費用、保険料、引越し費用など)を正確に把握する必要があります。諸費用の総額は新築で物件価格の3〜7%、中古で5〜10%程度が目安となります。
諸費用の主な内訳は以下の通りです。仲介手数料は物件価格の3%程度、登記費用は20〜30万円程度、火災保険料は年間数万円、引越し費用は10〜30万円程度を見込んでおきましょう。
諸費用も含めて住宅ローンの借入ができるケースが多く、頭金とは別に諸費用を準備する必要は必ずしもありません。ただし、諸費用分も借り入れる場合は、総借入額が増えることで月々の返済負担も重くなる点に注意が必要です。
また、金融機関によっては、物件価格だけ借入する場合と諸費用も含めて借りれする場合で、金利など借入条件が変わる場合もあります。詳しくは金融機関の担当者に相談してみると良いでしょう。
新築マンションの場合は修繕積立基金、中古物件の場合はリフォーム費用など、物件の種類によって必要な諸費用も変わります。事前に詳細な見積もりを取得し、余裕を持った資金計画を立てることが重要でしょう。
STEP4:ライフプランを踏まえて無理のない予算を設定
将来の収入変化や支出増加を見込んだ現実的な予算設定を行います。子どもの教育費、親の介護費用、転職リスクなどを考慮し、返済比率25%以下、年収倍率5倍以下での予算設定が理想的といえるでしょう。
返済比率や年収倍率は、収入状況によって異なります。具体的には、高所得者は返済比率を少し上げても問題がない場合が多いといえます。
ライフプランを考える際は、以下の要素を検討してください。教育費は子ども一人当たり1,000万円以上かかる場合もあり、住宅ローン返済と重なる時期の家計圧迫要因となります。また、親の介護費用や自身の老後資金についても早い段階から準備が必要です。
転職や病気による収入減少リスクも考慮に入れましょう。現在の収入を前提とした返済計画だけでなく、収入が減少した場合でも対応できる余裕のある予算設定が安心につながります。
STEP5:予算内で探す or 専門家に相談する
設定した予算内で物件探しを開始します。希望条件とのバランスが取れない場合は、エリアや築年数などの条件見直し、またはファイナンシャルプランナーなどの専門家への相談を検討したいところです。
物件探しでは、立地・広さ・築年数・設備などの優先順位を明確にすることが大切です。すべての希望を満たす物件を予算内で見つけるのは困難な場合が多いため、妥協できる部分と譲れない部分を整理しておきましょう。
予算と希望条件のバランスが取れない場合は、専門家への相談も有効な選択肢です。ファイナンシャルプランナーは、家計の状況を詳しく分析し、最適な予算設定をアドバイスしてくれます。また、不動産会社の担当者と連携することで、予算内で最適な物件を効率的に探すことも可能になるでしょう。
【年収別】住宅購入の予算目安
住宅購入の予算を検討する際は、実際の購入者データを参考にすることが重要です。住宅金融支援機構の調査によると、フラット35利用者の購入実績は住宅種別によって大きく異なります。
<住宅種別別の購入実績データ>
|
住宅種別 |
平均世帯年収 |
平均購入価格 |
年収倍率 |
総返済負担率 |
|
注文住宅 |
661万円 |
3,719万円 |
5.6倍 |
22.7% |
|
土地付注文住宅 |
736万円 |
4,851万円 |
6.6倍 |
24.3% |
|
建売住宅 |
594万円 |
3,716万円 |
6.3倍 |
23.5% |
|
新築マンション |
859万円 |
5,279万円 |
6.1倍 |
23.0% |
|
中古戸建 |
536万円 |
2,536万円 |
5.3倍 |
20.3% |
|
中古マンション |
659万円 |
3,037万円 |
5.6倍 |
19.9% |
実際の利用者データでは総返済負担率が平均23.4%となっていますが、長期的な家計の安定を考慮すると20%以下での予算設定が理想的です。以下は返済比率20%を基準とした年収別の予算目安になります。
<返済比率20%の場合の年収別予算>
|
年収 |
月収(手取り概算) |
月返済額目安 |
借入可能額目安 |
|
400万円 |
27万円 |
5.4万円 |
1,800万円 |
|
500万円 |
33万円 |
6.6万円 |
2,200万円 |
|
600万円 |
40万円 |
8.0万円 |
2,700万円 |
|
700万円 |
46万円 |
9.2万円 |
3,100万円 |
|
800万円 |
53万円 |
10.6万円 |
3,500万円 |
※借入期間35年、金利1.3%で試算
住宅の種類によって年収倍率や返済負担率に違いがあるため、購入を検討している住宅のタイプに応じて適切な予算を設定することが大切です。実際の購入者データを参考にしつつも、家計の安全性を重視した予算計画を心がけましょう。
苦しい支払いとならないために!住宅ローンを組む際の注意点

住宅ローンは長期間にわたる返済となるため、契約時に見落としがちなポイントがいくつかあります。後悔しない住宅ローン選びのために、以下の注意点を必ず確認しておきましょう。
住宅購入後の「維持費・税金」も月々コストに含める
住宅ローン返済以外の継続的な維持費用(固定資産税、保険料、修繕費、管理費など)も予算に含める必要があります。戸建で月3〜5万円、マンションで月4〜6万円程度の維持費を見込みたいところです。
固定資産税は物件価格によって変わりますが、年間10〜20万円程度が一般的です。火災保険料は年間数万円、地震保険を付帯する場合はさらに費用がかかります。
戸建住宅の場合、外壁塗装や屋根修理などの大規模修繕が10〜15年周期で必要になり、一回当たり100〜200万円程度の費用がかかることもあります。マンションでは修繕積立金や管理費が毎月発生し、築年数とともに金額が上がる傾向にあるでしょう。
維持費を含めた総返済額で家計への影響を判断することが、無理のない住宅購入のために重要です。
変動金利は”金利上昇後”の返済額も想定しておく
変動金利選択時は将来の金利上昇リスクを十分に検討する必要があります。金利が1%上昇した場合の返済額増加を事前に計算し、5年ルールや125%ルールなどの仕組みも正しく理解しておきたいところです。
変動金利は固定金利より低く設定されているため、当初の返済負担を抑えられるメリットがあります。しかし、経済情勢によって金利が上昇するリスクも存在するのです。
5年ルールとは、金利が変動しても5年間は返済額が変わらない仕組みです。125%ルールとは、返済額が見直される際も、従来の返済額の125%を上限とする制度になります。ただし、金利上昇分の利息は未払い利息として元本に組み込まれるため、将来の返済負担が重くなる可能性があるでしょう。
金利上昇に備えて、繰上返済用の資金を確保しておくか、固定金利への借り換えも検討材料として考えておくことが大切です。
繰上返済は”貯金を残しながら”が鉄則
繰上返済実行時も生活費6ヶ月分以上の貯蓄は必ず確保してください。住宅ローン控除との比較検討や、全体的な資産運用戦略の中での判断が重要となります。手持ち資金をすべて繰上返済に充てるのは危険といえるでしょう。
繰上返済には利息軽減効果がありますが、手元の現金が減ることで急な出費に対応できなくなるリスクもあります。病気や失業などの不測の事態に備え、最低でも生活費6ヶ月分の緊急資金は確保しておくべきです。
住宅ローン控除を受けている期間中は、控除額と繰上返済による利息軽減効果を比較検討する必要があります。控除額の方が大きい場合は、繰上返済を急がず、余剰資金を資産運用に回す方が有利な場合もあるのです。
繰上返済のタイミングは、家計の状況や金利動向を総合的に判断して決定することが重要になります。
まとめ

住宅購入予算の決め方は、まず現在の家計状況を正確に把握することから始まります。金融機関が提示する借入可能額と、実際に無理なく返済できる金額は別物です。将来のライフプランを考慮した現実的な予算設定が重要になります。
年収別の予算目安は参考程度に留め、個々の家計状況に応じて判断してください。住宅ローンを組む際は、維持費や税金、金利上昇リスクも検討し、無理のない返済計画を立てることが長期的な安心につながります。
住宅購入は人生で最も大きな決断の一つです。家計の状況や将来設計は人それぞれ違うため、不安や疑問がある場合は、専門家に相談することで、安心できる購入計画を立てられます。
専門家への相談をお考えの方は、こちらもご参考ください。
https://www.sakurajimusyo.com/expert/soudan.php