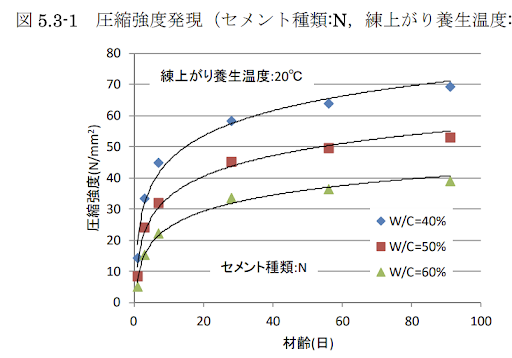快適な住まいづくりにおいて、適切な断熱性能を確保することは今や必須となっています。そして「断熱材をどう選ぶのか?」という点は、関心のある人も多く、重要なポイントといえるでしょう。
今回ご紹介する「グラスウール」は、住宅の断熱材のなかで最も使われている素材です。「グラスウール」にもいくつかの種類があり、それぞれに特徴や施工における注意点があります。
施工精度が伴わなければ適正な性能を発揮できない素材ですが、逆に正しい施工が行われればコストパフォーマンスの良い優れた断熱材ともいえます。
今回は「グラスウール」の特徴や種類、施工における注意点まで網羅し、解説していきたいと思います。
断熱性・防音性に優れた環境にやさしい素材「グラスウール」

グラスウールは、住宅の断熱材として最も普及しているものであり、さまざまな優れた点があります。そんなグラスウールとはどんな素材なのか?解説していきます。
グラスウールはどんな素材?
グラスウールとは、原料であるガラスを繊維状に加工した断熱材のことです。細かい繊維の組み合わせが動かない無数の空気層を形成し、それらが熱の移動を抑制することで断熱性能を発揮します。グラスウール製品は、袋詰めのものや裸状のものなどさまざまな形状があります。繊維を細くすることで、内部の空気層の数を増した「高性能グラスウール」も広く普及しています。
グラスウールの多くは、原料にリサイクルガラスを使っていることなど、環境にやさしい素材としても知られているとともに非常に軽量であり、自由に切ったり曲げたりできる加工性のよさも特徴のひとつです。
どんなところに使われているの?
 グラスウールは、おもに建築物の天井や壁、床などに入れて「断熱材」として使われます。
グラスウールは、おもに建築物の天井や壁、床などに入れて「断熱材」として使われます。
その他にも、建築物の内部に通る空調ダクトや排気ダクトなどの周囲を囲うことで、断熱や保温、保冷の効果が期待できます。また、吸音性にも優れており、音楽スタジオや体育館、工場などの壁・天井に施工すると、外部への音漏れを防ぐ防音材として効果的です。
グラスウールの性能・特徴は?
グラスウールは、その素材が生かされた優れた性能や特徴があります。おもな性能や特徴は以下の通りです。
断熱性について
グラスウールは、ガラスを繊維状に加工されており、その繊維が複雑に絡み合うことで、内部に無数の空気室を持つ構造となっています。そもそも空気は断熱性が高く、動かなければ効果的に熱移動を抑えられます。ところが、空気が動く環境にある場合は、熱を遠くまで、そして素早く運んでしまうため、断熱効果は期待できません。グラスウールの内部には、動かない空気室が無数に存在することにより、優れた断熱性を発揮するのです。
なお、グラスウールの断熱性は、密度や厚さ、繊維の太さなどに影響を受けるため、材料によって性能は異なります。
防音性について
グラスウールは、防音性にも効果的です。音は、物体が振動することにより、空気のような気体だけでなく、液体や固体などを媒介して伝わります。しかし、グラスウールは内部には無数の空気室があり、これらに音が到達すると、振動する空気に抵抗が生じて吸音効果を発揮します。
防水(撥水)性について
グラスウール本体は、水分を含むと性能を発揮できなくなるという特徴を持っています。
しかし、種類によっては、特殊な加工を施して撥水効果を付加したものがあります。撥水グラスウールを使うと、仮に水に塗れた場合でも速やかにはじいてくれるうえ、カットした場合でもその効果は損なわれません。また、防湿フィルムの袋に入ったグラスウールも、一定の防水性が期待できます。
価格について
グラスウールは、他の断熱材と比較しても材料費が安いという特徴があります。また、軽量で加工性がよいことから、施工費も安く抑えられ、工事費を抑えるには非常に適した材料といえます。
グラスウールの種類や選び方は?

グラスウールには、いくつかの種類があり、それぞれ特徴が異なるため、シーンによって使い分ける必要があります。ここでは、おもな種類と選び方について解説いたします。
グラスウールの種類
●表皮材無しグラスウール
表皮材無しグラスウールとは、素材がむき出しとなっている、いわゆる「裸品」と呼ばれるものです。用途としては、建築物の壁や天井、床などに充填したり、あるいは敷き込んだりして使います。壁へ施工する場合は、壁内結露を防止するため、グラスウールを充填後、その上へ透湿防水シートを張って気密層を設ける施工方法が一般的です。
●防湿層付きグラスウール
防湿層付きグラスウールとは、グラスウールを防湿フィルムの袋に入れたものです。用途としては、このタイプも建築物の壁や天井、床などに充填したり、あるいは敷き込んだりして使います。
表皮材無しグラスウールは、充填後に透湿防水シートを張って気密層を設ける必要がありますが、袋入りの場合は基本的に行いません。また、皮膚に接触するとチクチクしたりかゆみが生じたりすることがありますが、袋入りはそのような心配をすることなく施工できます。
●グラスウールボード
グラスウールボードとは、グラスウールをボード状に形成しているもので、素材がむき出しの「裸品」や、表面にガラスクロスを貼った「ガラスクロス額縁貼り」などがあります。用途としては、床に敷きこんだり、また「ガラスクロス額縁貼り」は防音を目的として壁や天井に仕上げ材として使用したりします。
●吹込み用グラスウール
吹込み用グラスウールは、「吹込み工法」用として、グラスウールを細かな綿状にしたものです。「吹込み工法」は、専用の吹込み装置を使い、天井裏に敷き込んだり、あるいは壁内に吹き込んだりすることで、断熱層を形成する工法となります。厚さは自由に設定できることや、隙間なく隅々まで施工できることなどが、この工法のおもな特徴です。
グラスウールの選び方
グラスウールにはさまざまな種類があります。そのため、種類を選ぶときにはポイントを押さえて決定することが重要です。
●断熱性は「密度」「繊維の太さ」がポイント
グラスウールの断熱性は、種類によって異なります。とくに、「密度」「繊維の太さ」などは、断熱性に大きな影響を与える要素です。「密度」は、高くなるほど内部の空気室が細分化されるため、熱が移動しにくく断熱性も向上します。
グラスウールの密度には10~96K(K=kg/m3)まで多くの種類が用意されており、その数値が大きくなるほど断熱性が高いと判断することが可能です。また、同じ密度でも「繊維の太さ」が細くなるほど、さらに内部の空気室が細分化され断熱性が向上します。
通常のグラスウールよりも繊維が細いものを「高性能グラスウール」といい、断熱性をより重視するならこのタイプで高密度のものを選ぶとよいでしょう。
●断熱性は「厚さ」もポイント
グラスウールの断熱性は、厚さにも影響を受けます。「密度」や「繊維の太さ」が同じもので比較すると、厚さに比例して断熱性も高くなります。つまり、より高い断熱性を確保したいのであれば、厚さを増せばよいということです。
しかし、厚さには限界があり、とくに壁の厚さを増すと室内は狭くなってしまいます。よって、限られた厚さのなかで、断熱性を高めるには、材料そのものの性能を高めることが必要となります。
●「裸品」と「袋入り」で性能に差はない
グラスウールの「裸品」と「袋入り」を比較した場合、基本的に性能面で差が生じることはありません。これらの大きな違いとなるのは、おもに施工性です。
「裸品」は、充填後に湿気が侵入して結露が発生しないよう透湿防水シートを張って気密層を設けますが、「袋入り」は防湿フィルムと一体となっているため施工時の手間を省けます。要するに、「裸品」と「袋入り」の違いは施工時の手間であり、製品としての性能は同レベルと考えられます。
グラスウールと他の断熱材の性能比較

断熱材の断熱性能は「熱伝導率」の数値で比較することができます。
熱伝導率とは、物質が熱をどの程度伝えやすいのか数値化したもので、その数値が小さいほど断熱性能が優れています。グラスウールとほかの断熱材で、熱伝導率にどの程度違いがあるのか見てみましょう。
断熱材の種類別 熱伝導率(単位:W/mK)
- グラスウール16K:0.045
- グラスウール32K:0.036
- 高性能グラスウール16K:0.038
- 高性能グラスウール32K:0.035
- ロックウール:0.038
- セルロースファイバー:0.04
- 押出法ポリスチレンフォーム3種:0.028
- ウレタンフォーム2種1号:0.023
- 吹付け硬質ウレタンフォームB種:0.026
熱伝導率の違いの他に、グラスウールの厚みでも性能が変わります。熱伝導率が同じでも、75mmより100mmの方が性能は良くなります。
グラスウールは施工方法が難しい。チェックポイントとは?

グラスウールの断熱工事には繊細な施工精度が求められ、間違った施工が行われると本来の性能を発揮できません。また、施工する人によって性能に差が生まれやすいため注意が必要です。
施工における特に重要なポイントを3つにまとめましたので、順に解説をしていきます。
①隙間ができていないか?

断熱性能は魔法瓶のように連続した断熱材や断熱層ですっぽりと覆うことが必要です。隙間が生じると、そこから熱が逃げてしまうため、いくら性能の高い断熱材を使っても期待する効果を得ることはできません。
グラスウールの施工は、柱と柱の間や、柱とサッシの間など、幅が一定でないため、必要な大きさでカットして設置することが一般的です。少しでも小さくなると隙間が生じ気密性は低下します。したがって、材料が小さくならないようぴったりのサイズで設置する必要があるのです。
②内部の空気層がつぶれていないか?
グラスウールは繊維の組み合わせで内部に無数の空気層をつくることで断熱性能を発揮します。ところが、グラスウールの施工段階で押しつぶすように設置すると、内部の空気層までつぶれてしまい断熱性能は著しく低下します。
グラスウールを大きくカットしてしまった場合、柔らかい材料であるため押し込むことも可能ですが、断熱材のキモでもある空気層まで潰してしまうと著しく性能が落ちるため注意が必要です。
③連続した防湿層は確保されているか?
グラスウールは、濡れると断熱性能が著しく損なわれます。住宅の壁のなかでグラスウールが濡れる現象は実際に起こることですが、その多くは結露が原因です。壁内で起こる結露は建物にとって非常に厄介で、断熱材だけでなく構造にも悪影響を及ぼすことがあるため、防がなくてはいけません。
そこで効果を発揮するのが連続した防湿層です。グラスウールと内装仕上げ材(石膏ボード+クロス)の間に連続した防湿シートの層をつくることでグラスウールの濡れを防止します。
袋詰めのグラスウールは防湿シートにくるまっていますが、壁に充填し隙間が生じない防湿テープなどでふさぎながら固定しなければいけません。裸状のグラスウールの場合は、壁に充填後、壁全体を防湿シートで覆う必要があります。
もし防湿層に隙間や破れがあると、そこから水分を含んだ空気が侵入し壁内で結露を起こす可能性は高まるでしょう。また、スイッチやコンセントの周辺についても、同様に細心の注意を払う必要があります。防湿層に欠損が発生しないよう、確実に連続した防水層を確保することが正しい施工方法になります。
正しい施工にはプロによるチェックや知識・技術も必要

さくら事務所が実施する年間100棟以上の新築検査実施では、実に『75%以上で施工ミス』が見つかっており(断熱材検査では、指摘率は実に81%以上)、一般の方の目では中々チェックが難しいのも住宅購入の悩ましいところです。
グラスウールの特性を生かし、コストパフォーマンスの良い断熱材として利用するためにも、施工ミスがあることを想定した上での、プロによる第三者チェックサービス“新築工事中ホームインスペクション(第三者検査)“は非常に効果的です(引き渡し前の施主検査も含みます)。
当社ではこのような事態を防ぐためのサービスを複数提供おり、工事中のミスや手抜きを未然に防ぐため、建物に精通したホームインスペクター(住宅診断士)が、専門的に工事現場(施工)のチェックを行っております。ぜひこの機会にご検討いただけると幸いです。