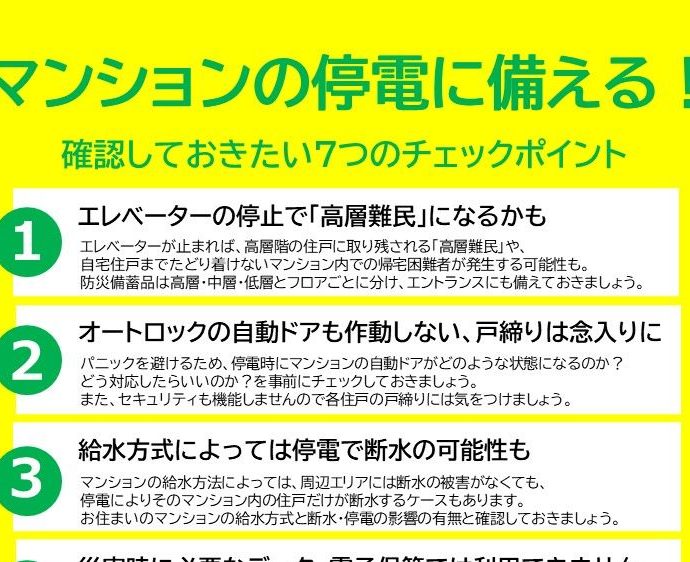年末の大掃除は、新しい年を気持ちよく迎えるための大切な行事です。普段は見落としがちな場所もこの機会にしっかり掃除することで、家の中を清潔に保つことができます。そして、大掃除の際に特に注意したいのが「カビ」。カビは見た目の問題だけでなく、健康や建物の耐久性にも影響を及ぼす厄介な存在です。
さくら事務所では、昨年9月に比べて、湿気のご相談が3.5倍、カビの相談が2.5倍にも増加しています。ご相談は、築年数3年未満の戸建てで特に増えているため、新しい住宅にお住まいの方も注意が必要です。
カビの発生には「結露」が深く関係しており、これを防ぐことがカビ対策のカギとなります。本記事では、結露とカビの関係や対策方法、さらにカビの掃除方法について詳しくご紹介します。年末の大掃除をきっかけに、カビを徹底的に退治し、快適な住環境を整えましょう!
結露でカビが発生するメカニズムとは
まずは結露でカビが発生するメカニズムについて解説いたします。
論点を整理すると、ポイントとなるのは以下の2点です。
- どのように結露が起こるのか
- どのようにカビが発生するのか
これらポイントについて詳しく見ていきましょう。
どのように結露が起こるのか
結露が起こるのは2つの要素が関係しています。
- 建物内外の温度差が大きい
- 室内の湿度が高い
空気中には、ある一定量の水蒸気を含むことができますが、限界となる水蒸気量を「飽和水蒸気量」といいます。
「飽和水蒸気量」は温度によって変化し、温度が高いほど量が多く、また温度が低いほど量が少なくなることが特徴です。
そして多くの水蒸気を含んだ空気が急激に冷やされると、蓄えられる限界量を超え押し出されるように水滴となって現れます。
この空気中の水蒸気が、温度の低下によって水滴となって現れる現象が「結露」です。
暖房された室内で湿度が高まると、空気は多くの水蒸気を含んだ状態になります。
そこで外部温度の影響を受けやすい窓付近で急激に冷やされると、蓄えられる限界量を超えて水滴になって現れるのです。
また温度差が大きくなるほど水滴の量も増えることになります。
どのようにカビが発生するのか
カビ菌はあらゆる場所に潜んでいますが、繁殖しやすい環境には4つの要素が条件となります。
- 栄養分がある
- 酸素がある
- 適度な温度
- 水分がある
以上4つの要素が揃うことでカビは繁殖します。
したがって「栄養分」「酸素」「温度」「水分」のうち、いずれかを排除することがカビ対策として効果を発揮するということです。
ただし、これら要素のうちコントロールすることが難しいものがあります。
コントロールが難しいものとは、「栄養分」「酸素」「温度」です。
カビは、ほこりや食べかす、木材などあらゆる物質を栄養分にするため完全に排除することはできません。
酸素は空気中に存在するものです。
またカビが繁殖しやすい温度は、人間が生活を送るうえで適温でもあるため、この要素を排除することも難しいでしょう。
唯一コントロールが可能なものは「水分」になりますが、その「水分」を供給する原因のひとつが「結露」になります。
要するに「結露」を防止することが、カビ対策として効果が高いといえるのです。
結露は2つの種類がある!
住宅で起こる結露は2つの種類があります。
- 表面結露
- 内部結露
表面結露とは窓周辺部など表面に現れる結露のことをいい、内部結露とは視覚的に確認できない壁の内側で起こる結露のことをいいます。
表面結露は、放置するとカビの繁殖につながり、ハウスダストアレルギーの原因になるなど健康被害を引き起こすこともあります。
内部結露は、放置するとカビの繁殖はもちろん、断熱材の効果を損ねたり、構造を腐朽させたりするなど、ときには建物に大きなダメージを与える現象です。
結露は目に見える範囲だけでなく見えない部分にまで影響を与えるため、知らないうちに症状が進行していることもあるのです。
カビを発見したら、表面結露だけでなく内部結露が起こっている可能性もあります。
知らないうちに状況が悪化しないよう、結露が起きにくい環境づくりを心がけるようにしましょう。
効果的な結露対策2選
結露対策として効果的な2つの方法をご紹介いたします。
結露が起こる要素を排除することを目的とした方法です。
- 換気
- 窓の断熱強化
換気
換気は結露が起こる要素「室内の湿度が高い」状況を排除することを目的とする方法です。
暖房で暖められ多くの水蒸気を含んだ空気を外部に排出することで、室内の湿度を下げる効果があります。
ただし換気は、「熱交換器」がついていないタイプだと外部温度の影響を受けるため、暖房効率は下がります。
したがって、ストーブなど燃焼系暖房機器の使用や洗濯物の室内干しを控えることなど、できるだけ湿度を高めないようにすることも必要になるでしょう。
窓の断熱強化
窓の断熱強化は、結露が起こる要素「建物内外の温度差が大きい」状況を排除することを目的とする方法です。
建物の内外で熱の移動を抑えることで、室内の空気温度の低下を防げます。
そして建物で最も熱の移動がある場所といえば窓です。
したがって窓を断熱強化することが最も結露対策として効果が期待できるわけです。
窓を断熱強化するには、インナーサッシ(内窓)の設置や複層ガラス窓との入れ替え、アルミではなく樹脂性のサッシを利用するなどいくつかの方法があります。
コストも比較的安く手軽に取り組めるため、結露に悩んでいるのであれば検討してみてはいかがでしょうか。
カビの掃除方法とは?
カビの発生は、結露対策をすることで一定の効果を発揮します。
では発生してしまったカビはどのように対処すればよいのでしょうか?
ここからは、カビが発生した場合の部位ごとの掃除方法についてご紹介したいと思います。
窓のカビ掃除
カビがまだ初期段階であれば中性洗剤を水で薄めてふき取ることで落とせます。
ふき取りが完了したら、アルコールを吹き付けて殺菌し再び繁殖するのを防止しましょう。
ゴムの部分など落ちにくい場合は、専用のカビ取り剤か漂白剤を使います。
その場合は、換気をすること、マスクやゴム手袋の着用をすることなど、安全への配慮も重要です。
カーテンのカビ掃除
結露は窓付近で起こりやすいため、カーテンにもカビが発生することがあります。
カーテンにカビが発生した場合は、漂白剤を使ってぬるま湯で洗濯を行います。
しっかり乾燥させたら、アルコールを吹き付けて殺菌し再び繁殖するのを防止しましょう。
また日常からこまめにアルコールを吹き付けて除菌しておくと、カビ対策として効果的です。
壁紙のカビ掃除
壁紙のカビは、初期段階でればアルコールを吹き付けてふき取ることで落とせますが、それでも落ちない場合は中性洗剤を水で薄めて軽くこすります。
激しくこすると壁紙の損傷につながるため、力加減には注意して行いましょう。
ただし壁紙のカビで症状が著しい場合は、発生原因を究明する必要があります。
というのも雨漏りや内部結露が原因であれば、カビだけでなく構造を傷める可能性もあるためです。
場合によっては、専門家による調査を検討することが必要かもしれません。
フローリングのカビ掃除
フローリングの場合は一般的にワックスを塗っているため、剥がさないよう中性洗剤を水で薄めてふき取るようにしましょう。
それで落ちない場合はワックスを剥がしてカビを除去する必要があります。
その場合、色落ちなどフローリングを傷める可能性もあるため、プロの業者に依頼するほうが賢明かもしれません。
またワックスを塗りなおす場合は、一旦既存のワックスを全部剥離するか、あるいはピースに限定して剥離し、そのうえで実施することがポイントです。
中途半端に剥がれた状態で塗りなおすと、ムラになって目立つためしっかりと事前準備を行いましょう。
まとめ
住宅のカビ対策で重要なことは、結露を抑えることにあります。
また結露は、カビだけでなく建物の耐久性を損ねる原因にもなるため、しっかりと対策をしなくてはいけません。
湿気は建物にとってリスクになるため、結露がよく起こる場合は大掃除のタイミングなど、定期的に建物の健康状態を調査することをおすすめいたします。
建物に精通した専門家によってコンディションをチェックする「ホームインスペクション(住宅診断)」をご検討ください。